【合格者が教える】大阪大学の英語二次試験の対策方法
この記事は「合格者が教える大阪大学の2次試験の英語対策法」です!
筆者の私は大阪大学の文系学部を受験し合格しました。
この記事は問題の形式が異なる、外国語学部以外の方は同じ対策ができると思いますので参考にしてみてください。
英語二次試験の構成
大阪大学の英語二次試験は90分の試験で大問は5個、英訳、和訳、文章読解が中心です。
単語の1つ1つはそれほど難しくありませんが、造語などに対して文脈から想像力を働かせて訳文を構築する能力が問われていると感じました。
試験の全体像と特徴
大阪大学の英語2次試験は90分の大問5つです。(大問は6つですが1つは外国語学部用です)
大問ごとの文章量は、共通試験に登場する長文と大差ありません。
長文はエッセーまたは説明文が出題されます。抽象的な表現が多く、後半の文脈から前半に戻り、意味を再定義していく能力が求められます。年度によりますが、医療系の単語や人体用語の単語(thumbs, digest)など、特定の分野を取り扱った長文が出される傾向にあります。
医療、歴史、化学、音楽、など過去問を数多く解くことで単語を収集していくことで対策が可能です。
単語の難易度はそれほど高くなく、共通試験対策用の単語帳を網羅すれば十分だという印象を受けました。
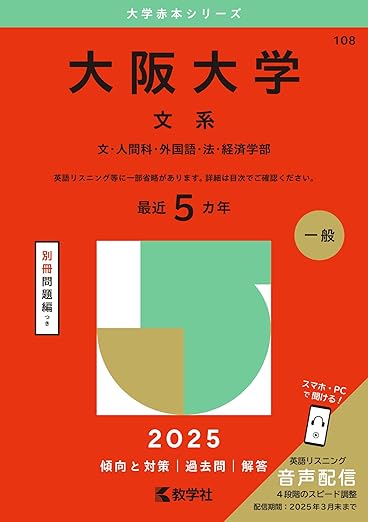

私の回答順
大阪大学の英語2次試験 - 90分
1番目 - 大問3 (長文読解) - 20分
2番目 - 大問4 (英文回答) - 15分
3番目 - 大問1 (和訳問題) - 15分
4番目 - 大問5 (英作文) - 15分
5番目 - 大問6 (英訳問題) - 15分
80分回答+10分見直し
*大問2は外国語学部用
大問1の英文は、前置詞や関係詞などの構造が複雑で時間がかかります。ここでつまずくと焦りが生じ、ミスが多くなりやすくなります。
従って、大問3の長文読解から回答するようにしていました。
また、英訳や和訳問題では、最初から完璧な文章を作るのではなく断片的に文章を作り、最後に一文にまとめるやり方を進めます。これは英訳(和訳)対象の一文が非常に長く、一気に考えるとミスが生じやすいためです。
私が使用した対策本や方法
![阪大の英語20カ年[第9版] (難関校過去問シリーズ)](https://m.media-amazon.com/images/I/71Cb7U9nglL._SY522_.jpg)
私は「阪大の英語20年」という赤本をメインに使用していました。
共通テストまでは中身をパラパラと見る程度でほぼ取り組まず、共通テスト終了後から時間制限を設けて解いていました。まず共通テストの英語を9割程度取れることに専心すれば、その後の二次試験対策もかなり楽に行えると思います。
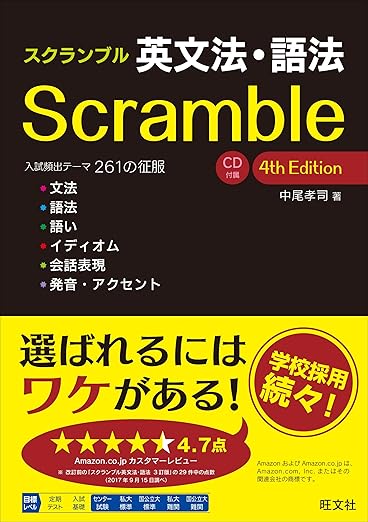
文法対策はスクランブルという文法書を高校で購入させられたので、それを3年間使っていました。1200問程度ありましたが分からなかった部分には全て付箋を貼って覚えました。

単語はValue1700を使用しました。こちらも高校で購入させられたもので、3年間使用しました。
大問で取り扱われる特定分野の単語を収集するための方法として、同志社大学の過去問を解くことも有効です。他の私大に比べて英語の難易度が高く、専門的な英単語がよく表れます。
![同志社大の英語[第10版] (難関校過去問シリーズ)](https://m.media-amazon.com/images/I/717RdvDNcwL._SY522_.jpg)
編集者が教えるおすすめ教材
このレベルの長文読解には BeCome Level6 がオススメです!
勘で正解できないような工夫がされている長文教材なのでオススメです!

執筆情報
筆者 : まるっこ
受験年 : 2019
さいごに
関連記事
【合格者が教える】神戸大学の英語二次試験の対策方法
【合格者が教える】千葉大学の英語二次試験の対策方法
【合格者が教える】東京理科大学の英語試験の対策方法
【合格者が教える】慶應義塾大学の英語試験の対策方法
【合格者が教える】名古屋市立大学の英語二次試験の対策方法
【塾講師が教える】北海道大学の総合理系入試の英語の対策方法
【塾講師が教える】京都大学の英語二次試験の対策方法
【塾講師が教える】大阪大学外国語学部の英語二次試験の対策方法
【塾講師が教える】兵庫県立大学の英語二次試験の対策方法
【塾講師が教える】信州大学の英語二次試験の対策方法
【塾講師が教える】産業能率大学の英語試験の対策方法
【塾講師が教える】名古屋大学の英語試験の対策方法
【塾講師が教える】広島大学の英語試験の対策方法
【塾講師が教える】九州大学の英語試験の対策方法
【塾講師が教える】筑波大学の英語試験の対策方法
【塾講師が教える】東北大学の英語試験の対策方法

