【塾講師が教える】大阪大学外国語学部の英語二次試験の対策方法
この記事は「合格者が教える大阪大学外国語学部の英語対策法」です。
筆者の私は塾で大阪大学外国語学部だけでなく他大学の受験対策も行っていますのでその経験を活かした対策法を紹介したいと思います!
大阪大学外国語学部の英語は学部専用試験ですので、受験しようとしている人は参考にしてみてください。
試験の構成と特徴
・外国語学部はリスニングがあるため大問5問構成
・外国語学部の受験時間は120分
試験のレベルと特徴
・英文和訳(大問1)は旧帝大の中では標準的
・大問2の長文読解は難解。特に外国語学部の長文は語数が1,200語程度のため非常に時間がタイトで、かつ難易度も高い問題
解答のコツ / 解答順
大問1は(A)(B)に分かれており、それぞれ1〜2文程度の英文を和訳する問題です。文構造の理解はもちろんのこと、直訳では訳にならないことが多いため、訳しにくい表現も意味をよく吟味した上で日本語に丁寧に直していく作業が必要です。また短いながらの文脈があることも多いため、前後をしっかり読んだ上でどういった文脈でその単語が使われているのかというところまで拾って訳すことが求められています。
大問2は長文読解で、言い換え表現の選択問題・代名詞の示す内容を抜き出す問題・内容に関する記述問題などがあります。特徴的な言い換え表現の問題は難しい表現も多く、知らない表現が出てくることは十分にあり得ます。前後をしっかり読み込み、文脈から推測して選択することが必要です。選択式の問題は落とさないようにしましょう
大問3は自由英作文で、例年60〜80語程度の指定があります。テーマは一般的なものが多く、ある年の問題では「効率やスピードを追求することの是非」を自分で立場を選び記述する問題でした。
大問4は2問に分かれており、2問目は文学部受験者とそれ以外とで異なります。1問目は比較的取り組みやすい内容が多く、2問目は少し難易度の高い内容が出題されます。文のレベルの差はあれど、どちらも少し分量があり、また訳しづらい日本語(比喩や慣用句など)が含まれているため、直訳では対応できません。その表現の言わんとしていることが何かを見抜いた上で、その趣旨を訳していくという作業が必要です。
大問5のリスニングは2回読まれる音声に対して設問に日本語で答える形になります。設問は5問ありすでに問題用紙に書いてあるので要点を把握しておいてから必ずリスニングに入りましょう。
選択肢から回答を選ぶわけはないので難しいです。必ず対策しておきましょう。
私がオススメする対策本や方法
他の旧帝大と同様に、まず早い段階で1冊標準的なレベルの単語帳(システム英単語や速読英単語など)を仕上げてから、過去問などを解いていて不足を感じるようであれば2冊目の単語集にいくのも良いでしょう。外国語学部の場合は、『鉄壁』あたりまでやっている学生が多い印象です。

1000文字近い長文を解くことになるため、長い長文を解く練習もしておきましょう。
英文和訳には構文の理解が必須なため、『ポレポレ英文読解プロセス50』『英文読解の透視図』『英文解釈の技術100』等の教材で構文の知識を盤石にしましょう。
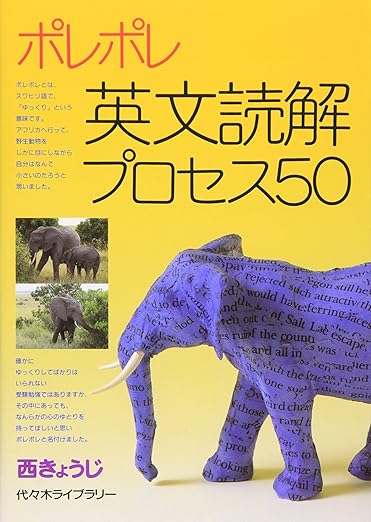

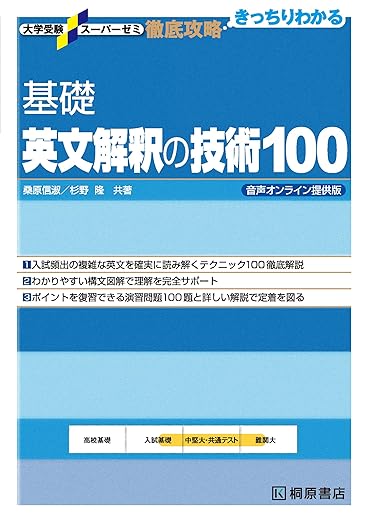
外国語学部のリスニングは、実際に受けると聞き取りづらく感じるため、共通テストのようにイヤホンをするのではなく、少し遠いところからスピーカーで音声を流すなどして、聞き取りづらい状況で練習をすることをおすすめします。個別試験向けのリスニング教材は少ないですが、『関正生の英語リスニングプラチナルール』がおすすめです。最後の方の問題は、阪大外語の長文リスニング対策への取っ掛かりにもなります。

過去問題
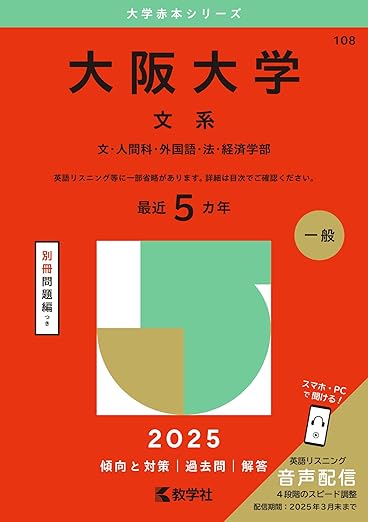
![阪大の英語20カ年[第9版] (難関校過去問シリーズ)](https://m.media-amazon.com/images/I/71Cb7U9nglL._SY522_.jpg)
執筆情報
筆者 : なめこ / 20代後半 / 塾講師
さいごに
関連記事
【合格者が教える】大阪大学の英語二次試験の対策方法
【合格者が教える】神戸大学の英語二次試験の対策方法
【合格者が教える】千葉大学の英語二次試験の対策方法
【合格者が教える】東京理科大学の英語試験の対策方法
【合格者が教える】慶應義塾大学の英語試験の対策方法
【合格者が教える】名古屋市立大学の英語二次試験の対策方法
【塾講師が教える】北海道大学の総合理系入試の英語の対策方法
【塾講師が教える】京都大学の英語二次試験の対策方法
【塾講師が教える】兵庫県立大学の英語二次試験の対策方法
【塾講師が教える】信州大学の英語二次試験の対策方法
【塾講師が教える】産業能率大学の英語試験の対策方法
【塾講師が教える】名古屋大学の英語試験の対策方法
【塾講師が教える】広島大学の英語試験の対策方法
【塾講師が教える】九州大学の英語試験の対策方法
【塾講師が教える】筑波大学の英語試験の対策方法
【塾講師が教える】東北大学の英語試験の対策方法

